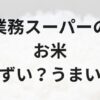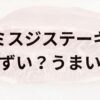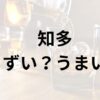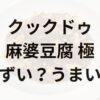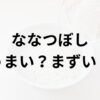陸稲はまずい?うまい?理由6選まとめと口コミも
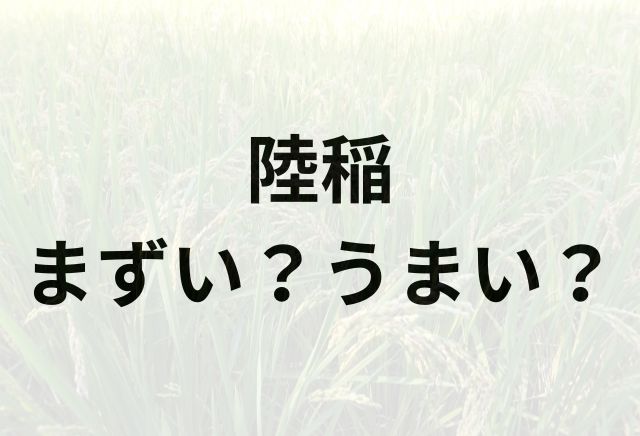
お米といえば水田で育つ「水稲」が一般的ですが、畑で育つ「陸稲(おかぼ)」という品種も存在します。
日本では古くから栽培されてきたものの、「水稲に比べてまずい」といわれることが多く、食卓で見かける機会は少なくなっています。
しかし、その背景には
・品種特性
が深く関係しており、一概に「まずい」と切り捨てられるものではありません。
本記事では、陸稲がなぜまずいと評されるのか、逆にうまいとされる理由、そして水稲との違いや美味しい品種について詳しく解説していきます。
陸稲とは

陸稲とは、水を張った田んぼではなく畑で育つ稲のことを指します。
かつては日本でも広く栽培され、戦後の食糧難の時代には重要な主食として活躍しました。
しかし、その特徴として「水稲に比べると粘り気が少なく、味わいが淡白」という点があり、現代の日本人が好む「もちもちしたご飯」とは異なる食感を持っています。
そのため「まずい」と評されることが多いのです。
とはいえ、陸稲には
・乾燥に強い
といった利点があり、地域によっては今でも受け継がれています。
また、品種改良によって食味が向上しているものもあり、一概に不味いと決めつけられない奥深さを秘めています。
まずい理由

粘り気の少なさ
陸稲は水稲と比較すると粘り気が少なく、炊き上がりがパサつきやすい特徴があります。
日本人は一般的に
・ねっとり
とした食感を好む傾向が強いため、この違いが「まずい」と感じられる要因になります。
おにぎりや白ご飯としては水稲のほうが適しており、陸稲は炊き込みご飯やチャーハン向きと言われることもあります。
味が淡白で香りが弱い
水稲は甘みと旨みが強く、炊きたての香りも豊かです。
これに対し陸稲は甘みが控えめで、香りも穏やかです。
料理によってはさっぱり感として評価されるものの、日常的に食べる主食としては
・味気ない
と感じる人が多いのです。
品質のばらつきが大きい
陸稲は水のコントロールが効かない畑で育つため、天候の影響を強く受けます。
雨が少なければ実入りが悪くなり、逆に降りすぎれば根腐れのリスクもあります。
そのため収穫された米の品質にばらつきが出やすく、安定して美味しい米を得にくい点が「まずい」と評される理由のひとつです。
保存性や鮮度による差
水分量が少ない陸稲は保存中に風味が落ちやすい傾向があります。
長期保存すると炊き上がりのパサつきがさらに強調され、時間が経つほど「まずい」と感じられることがあります。
昔の日本では保存技術が未発達だったため、この弱点がより目立っていたと考えられます。
日本の食文化とのミスマッチ
日本では昔から「お米は粘りがあってこそ美味しい」という食文化が根付いています。
そのため粘り気が少なく、ぱらっとした陸稲は文化的な好みに合わず、どうしても「まずい」と感じられてきました。
実際、世界的には陸稲に近いインディカ米が広く食べられていますが、日本では水稲のジャポニカ米が好まれています。
炊飯の難しさ
水稲と比べて炊飯の水加減が難しく、うまく炊かないとすぐに固くなったりパサついたりしてしまいます。
炊飯技術が進歩した現代なら調整可能ですが、昔はこの点も「まずい」と言われる要因のひとつでした。
うまい理由

さっぱりとした食感が料理を引き立てる
陸稲は粘りが少なく、炊き上がりがパラッと軽い仕上がりになります。
この特徴は日本人が好む「ねっとり・もちもち」とは異なるものの、実は料理に合わせると大きな利点となります。
たとえば、カレーライスでは水稲の粘りが強いご飯だとルーと絡まりすぎて重く感じることがありますが、陸稲は軽やかな口当たりで、スパイスの香りを邪魔せずに引き立ててくれるのです。
また、チャーハンでは水稲のご飯だとべたつきやすい一方、陸稲は自然にパラパラと仕上がり、まさに理想的な炒飯向きの米といえます。
さっぱりとした食感は、現代の「おかず重視」の食生活にも合っており、陸稲の魅力を再発見する人が増えています。
品種改良で進化する味わい
かつての陸稲は確かに「淡白で味気ない」と言われることが多かったのですが、近年は品種改良が進み、食味の良い品種が次々と登場しています。
代表的な「ハッピーヒル」は自然農法研究家の福岡正信氏によって育てられた品種で、陸稲でありながら粘りと甘みをバランス良く備えています。
その他、コシヒカリをベースにした陸稲系統や、各地域で復活栽培されている在来種など、食味評価で高い点数を得る品種も出てきました。
これらの努力によって「陸稲=まずい」というイメージは徐々に払拭されつつあり、むしろ「水稲とは違う美味しさを持つ」として再評価されています。
素朴で雑味の少ない風味
水稲はもちもちして甘みが強い一方、陸稲は淡白でシンプルな風味が特徴です。
これを「味が薄い」と否定的に捉える人もいますが、逆に「雑味がなく、素材そのものの味を邪魔しない」という利点でもあります。
出汁をきかせた和食、例えば煮物や焼き魚などと合わせると、陸稲のさっぱりしたご飯は驚くほど相性が良いのです。
また、味付けが濃い中華料理や洋風の肉料理でも、あっさりした陸稲が舌をリセットしてくれる役割を果たし、料理全体をバランス良く楽しめるようにしてくれます。
消化が良く健康的
陸稲は粘りが少ないため、消化吸収が比較的スムーズです。
そのため、胃腸に優しいご飯としても注目されます。
高齢者や子ども、あるいは消化に不安を抱える人にとっては、むしろ「うまい」より「体に合う」といった安心感を持つお米です。
また、カロリーは水稲とほとんど変わらないものの、軽やかな口当たりで食べ過ぎを防ぎやすく、ダイエットや健康管理を意識する人からも評価されています。
現代の「ヘルシー志向」に合致している点は、陸稲の強みといえるでしょう。
世界的な基準では主流の食味
日本では水稲(ジャポニカ米)のもっちり感が標準ですが、世界的に見るとインディカ米のように粘り気の少ない米が主流です。
つまり、陸稲の特徴は「世界基準の美味しさ」に近いともいえます。
インドやタイではカレーや炒め物に合わせてサラサラした米が好まれ、アメリカやヨーロッパでもパラッと炊き上がる米が支持されています。
陸稲も同様の特徴を持っているため、国際的な料理との相性は抜群です。
グローバルな食文化を楽しむ現代においては、「日本の基準でまずい」とされた陸稲が、実は料理を格段に引き立てる存在になり得るのです。
環境に強く未来的価値が高い
うまさは単に舌で感じる味だけではなく、食材としての持続可能性や安心感も評価基準のひとつです。
陸稲は畑で栽培できるため、水資源が乏しい地域や災害時でも育てられる強みを持っています。
気候変動や食料問題が懸念される現代において、陸稲の栽培可能性は極めて大きな価値を持ちます。
「環境に強く、安定して収穫できる」という特性は、結果的に人々の食を支える安心感につながり、その背景を知って食べるとより「美味しい」と感じられるのです。
口コミ

まずい・美味しくないと言う口コミ
ただの陸稲なら基本的にまずいコメになります
— デブの細道 (@DebuToSlim) April 21, 2025
明後日の感想。陸稲はまずいです。あまり食べたことないでしょうが、今流通しているお米と別物です。
蓮華でも植えて緑肥にしたらダメなのかしら?— 硯石 (@suzuri1212) August 30, 2024
昔、近所に大水が出て、新しい住宅地が流された時、陸稲のおにぎりを差し入れたら
『こんな不味いもん食わせやがって」と
散々文句言われたらしい。美味いものを喰いなれた方々には、陸稲はクッソまずいもので、嫌がらせに思えたんだろうね
#親父熱愛— ミサイル姉妹☆妹☆みけにゃんこ (@GudeNyanko) August 19, 2017
陸稲栽培するの?水稲に比べて美味しくないよ。 https://t.co/GAOj42uNva
— 鷲塚与太八郎 (@mushokuchuunen) July 27, 2017
うまい・美味しいと言う口コミ
豪州米は大半が陸稲だけど、丁寧に研いで日本製の炊き方が微調整できる炊飯器で追い込んでやると、結構うまいです。陸稲でいいのでは?
— kaz hagiwara(萩原 一彦) (@reservologic) September 20, 2023
陸稲はうまいのよ。今日本であるのかな?
— norihiko yamada (@yamalao) March 26, 2010
村のごはん。米は陸稲。すごく美味しい。湖のほとりで、湖で獲れた魚、キャッサバの葉を叩いたもの、筍、ピンクのはトーチジンジャーの花と実を和えたもの。調理には竹筒を使う。そしてダヤックの料理は油が少なく、炒めたり揚げたりより煮たり蒸したりが基本なのだそう。 pic.twitter.com/Qh4HFIagYG
— Nao Nishimiya (@naonishimiya) August 19, 2022
美味しい陸稲のお雑煮も今朝が最後 pic.twitter.com/Woiat7IT2h
— ピーターとマロン (@peter0520) January 4, 2021
水稲との違い

栽培環境
水稲は水田に水を張って育てるのに対し、陸稲は畑で育ちます。
乾燥に強いのが特徴で、水資源が乏しい地域でも栽培可能です。
食感と味
水稲は粘りが強く、もちもちとした食感。
陸稲はさらっとしており、パサつきやすいが軽やかな食感です。
生産性と安定性
水稲は水田で安定した収穫が得られる一方、陸稲は天候の影響を受けやすく収量が不安定です。
食文化との相性
日本の和食は水稲と相性が良く発展しましたが、カレーや炒飯など国際的な料理には陸稲の特徴が向いています。
陸稲で美味しい品種

ハッピーヒル
自然農法研究家・福岡正信氏が育成した品種。
粘りと風味を兼ね備え、陸稲の中でも食味が良いとされます。
ともほなみ
北海道で開発された陸稲品種で、冷涼な気候でも安定した収量を確保できる強さがある。
炊き上がりはあっさりしており、丼物や炒飯など料理用に適した軽やかな食味を持つ。
トヨハタモチ
北関東~東北を中心に栽培される陸稲のもち米品種で、耐病性や栽培適応性に優れる。
粘りがしっかりしているため餅や和菓子に向いており、陸稲もち米として評価が高い。
まとめ
陸稲は「まずい」と言われがちですが、それは水稲との比較による側面が大きいです。
確かに粘りや甘みは控えめで、炊き上がりはパサつきやすい特徴があります。
しかし、逆にさっぱりした食感は炒めご飯やカレーに最適であり、品種改良によって美味しさも向上しています。
また、水を必要としない栽培特性は環境変化に強く、今後の食料問題の解決策としても期待されています。
「陸稲=まずい」という一面的な見方ではなく、用途や食文化に応じて評価すべき存在といえるでしょう。