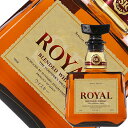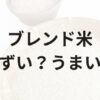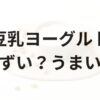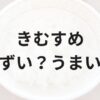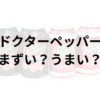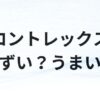サントリーローヤルはまずい?まずい理由6選まとめと口コミも
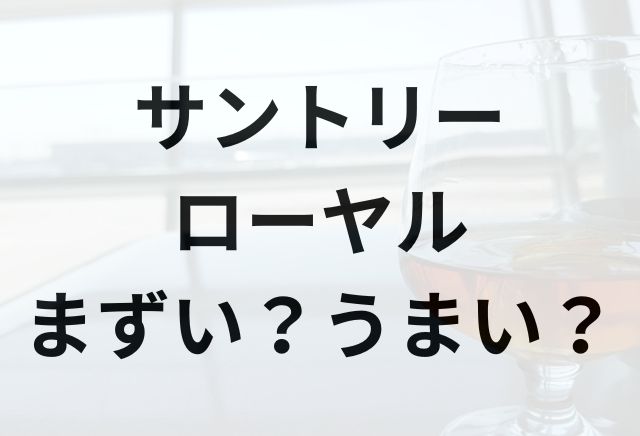
サントリーのウイスキーの中でも、長い歴史を持つ「サントリーローヤル」。
角瓶やオールドに比べるとやや高級ラインに位置し、かつては贈答用や特別な日に飲む一本として親しまれてきました。
しかし現代では
・甘ったるい
・期待したほどではない
といった声もあり、“まずい”と評価する人も少なくありません。
一方で
・昔ながらの日本のウイスキーらしい
と高く評価する人もいて、賛否が分かれる銘柄です。
この記事では、その理由を整理し、さらにおすすめの飲み方も紹介します。
サントリーローヤルとは

出典:https://products.suntory.co.jp
サントリーローヤルは、1960年にサントリー創業60周年を記念して発売されたウイスキーです。
当時の社長・鳥井信治郎の孫であり名ブレンダーとして知られる鳥井信一郎(佐治敬三)によってブレンドされました。
酒齢の長いモルト原酒を中心に、グレーンを組み合わせ、香りや味わいの調和を追求したのが特徴。
ボトルデザインも高級感があり、かつては贈答用ウイスキーの定番でした。
現在も一部販売が続いており、百貨店や酒販店で見かけることができます。
歴史を感じさせるクラシカルなブレンドで、サントリーの伝統を体現する一本です。
まずい理由

香りが古臭く感じられる
サントリーローヤルは1960年発売という歴史ある銘柄。
その分クラシカルなブレンドを守っているのですが、この香りが「古臭い」と言われてしまう理由でもあります。
今のトレンドであるフルーティーで華やかなアロマや、スモーキーな強さに慣れている人が飲むと、ローヤルのシェリー樽由来の甘い香りや、奥にあるウッディで落ち着いたニュアンスが
・紙のよう
・押し入れの匂い
などネガティブに受け取られがちです。
本来は熟成感として評価できる部分も、世代や嗜好が違えば「時代遅れの香り」と判断され、まずいと感じる大きな原因になります。
甘さがくどくて飲み疲れる
ローヤルの大きな特徴は、蜂蜜や熟した果実のような甘さ。それは一口目に
・優しい
と好印象になるのですが、飲み続けていくと
・飽きてくる
とマイナスに転じることがあります。
特に辛口やスパイシーなタイプを好む人には「ベタつく甘さ」にしか思えず、食中に合わせると料理の味を邪魔することも。
甘さが強いウイスキーは食後酒やデザート的な位置付けなら輝きますが、「メインの一杯」として選んだ人には重く感じやすいのです。
このギャップが「まずい」と評される理由のひとつです。
度数のわりにパンチがなく物足りない
ローヤルはアルコール度数43%。
数字上は標準的ですが、飲み口が非常にマイルドなので
・パンチが足りない
と感じる人が多いです。
スコッチのシングルモルトやバーボンのように力強い余韻を期待していると、ローヤルは穏やかすぎて“物足りなさ”が前面に出ます。
特にウイスキー愛好家やヘビードリンカーからは
・腰がない
と否定されがち。
まろやかさを狙った設計が、逆に刺激やキック感を求める層には不満点になってしまうのです。
価格に対して満足感が薄い
発売当時は高級ウイスキーの位置付けだったローヤル。
現在も2,000円台後半〜3,000円程度で売られることが多く、角瓶やオールドより一段上の価格です。
しかしその分「特別感」を期待すると、味わいがクラシカルで落ち着きすぎているため
・同じ値段なら海外のシングルモルトを買う
という声が出やすいです。
コスパ重視の人にとっては「わざわざローヤルを選ぶ理由が見つからない=まずい」という判断に繋がってしまうのです。
時代の嗜好変化で評価がズレた
ローヤルが登場した1960年代は、リッチで甘みがあり、丸い味わいこそ“贅沢”とされていました。
しかし現代のウイスキー市場は、スモーキーなアイラ系やシングルモルトの個性的なフレーバーが人気。
飲み手の舌が多様化している中で、ローヤルの“角がない穏やかさ”は
・没個性
と受け止められがちです。
時代を超えて変わらない設計は強みでもありますが、現代的な価値観ではそれが弱点となり、「古いウイスキー=まずい」と見られてしまうのです。
飲むシーンを選びすぎる
ローヤルは食中酒としては合わせやすいものの、単体で強烈な存在感を放つタイプではありません。
結果的に「食事と一緒なら悪くないが、一杯だけで楽しむには弱い」という評価になりがちです。
さらに、バーで飲むと他の銘柄と比べて地味に映り、家で一人で飲むと物足りない。
要するに“飲むシーンのハマり具合”に左右されやすいお酒です。
シーンを間違えると
・甘ったるい
・印象に残らない
とネガティブに感じられ、それが「まずい」という評価に繋がってしまうのです。
うまい理由

柔らかな口当たりで初心者でも飲みやすい
サントリーローヤルは、アルコールの角が丸くて口当たりが柔らかいのが大きな特徴です。
ストレートでもツンとした刺激が少なく、スッと舌に馴染みます。
そのため「ウイスキーは強いお酒」という印象を持つ初心者にとっても入りやすい一本。
・ローヤルなら飲める
という声が出るのは、この飲みやすさが理由です。
逆に言えば“パンチ不足”と批判される部分も、このやさしい飲み口を評価する人にとっては大きな魅力になっています。
蜂蜜やドライフルーツのような甘みが心地よい
ローヤルのブレンドは、蜂蜜や熟した果実を思わせる甘さが際立ちます。
特に口に含んだときのとろっとした甘みは、まるでドライフルーツやシロップ漬けの果物のよう。
香りの中にもほんのりレーズンやプラムを思わせる熟成感があり、甘さとともに落ち着きを感じさせてくれます。
この“甘みのある柔らかさ”は、スパイシーなウイスキーが苦手な人にとっては「うまい」と思える決定的な要素です。
チーズやナッツ、チョコレートなどと合わせても、その甘さが程よく寄り添ってくれます。
和食との相性が良い
スモーキーさや強烈なスパイシー感が少ないため、和食と一緒に飲みやすいのもローヤルの強みです。
焼き魚や煮物、天ぷらなどと合わせても味を壊さず、むしろ出汁や醤油の旨みに寄り添ってくれます。
特に水割りにすると、ほのかな甘みとやさしい香りが食事と自然に調和し、食中酒としての役割を果たします。
海外のウイスキーでは「料理と合わせにくい」と感じることもありますが、ローヤルは日本の食卓にスッと馴染む、いかにも“日本的なウイスキー”です。
贈答品として安心感がある
長い歴史と高級感のあるボトルデザインは、贈り物としての価値を高めています。
昭和の時代から
・お歳暮
・お祝いの品
として親しまれてきた背景があり、もらった側も
・信頼できる
と安心感を持ちやすいです。
実際の味わい以上に、贈り物としての“体験価値”が加わることで「やっぱりローヤルはうまいな」と感じられることも少なくありません。
世代を超えて愛される定番ブランドだからこその評価です。
ゆっくり変化していく香りが楽しめる
グラスに注いでから時間が経つと、最初に感じた蜂蜜や果実の甘さが落ち着き、次第に木の香りやほのかなスパイスが現れてきます。
ロックで少し氷が溶けるとさらにまろやかさが際立ち、水割りにすれば甘さの奥から柔らかな香りが広がる。
飲むスタイルや時間によって印象が変化していくので、ただ「甘いだけ」のお酒にとどまらない奥行きがあります。
こうした“変化を楽しめる余白”があることも、ウイスキーとしての魅力の一部です。
日本のウイスキー史を味わえる一本
サントリーローヤルは1960年に誕生し、日本人が“高級ウイスキー”に求めていた味を形にした一本です。
当時の時代背景や嗜好を今に伝えており、現代のシングルモルト人気やアイラブームとは別軸の価値を持っています。
いま飲むことで「昭和の日本人が好んだ贅沢な味」を追体験できるのは、歴史ある銘柄ならではの楽しみ。
単なる味覚の評価にとどまらず、“文化や物語を含めて味わえる”という点で「ローヤルはやっぱりうまい」と感じる人が多いのです。
口コミ

まずい・低評価な口コミ
ラウンジのサントリー・ローヤル。。。これがまずい。ウイスキー好きのオレが匙を投げるレベル。
— onom (@onomoto) September 4, 2011
サントリーのウイスキーって知多以上じゃないとあまり美味しくないよな
ローヤル、リザーブ、オールド飲んだけどどれもパッとしなかった— tadanosalaryman (@y03k) June 26, 2024
特級表示のサントリーローヤルですね。飲めるには飲めるけど、味はあんまり美味しくないかもしれませんね。アルコールのコシが抜けて緩い味になってるかもしれませんね…(((^^;)
— matayoshiya (@HitodenasiYa3) January 22, 2019
アイスクリーム食ってから飲んだサントリーローヤルが美味しくないので、コレはやはり甘いモノと合わせるウイスキーではないな
— COE (@coe900ss) January 2, 2022
うまい・高評価な口コミ
サントリーローヤル15年開けちゃった
ちなみにクソうまい pic.twitter.com/C6kgUhDzHd— あなソ (@M4tsushita) November 11, 2023
うまい!サントリーローヤル60もSRもうまいよぉ( ;∀;)
またひねてませんでした(笑)
まだ敗北を知らない(知りたくはない)SRが二本になったんでちびちび飲みから大胆に飲みたいんですが何が良いですかねぇ?#TWLC pic.twitter.com/nuQRqirKXk
— たっきー (@uaQ6rRY8qvNifqh) April 18, 2021
サントリーローヤル久々飲んだらばかうまい
— greeeeen_niki (@green900r) April 11, 2021
飲むか😁
サントリーローヤルはうまいー pic.twitter.com/kO1pBPUDEj— 自由に生きよう 鷹 (@nomadlife358) August 12, 2025
結局サントリーローヤルがうまいってなってる pic.twitter.com/26LWxQnbW6
— ミョウバン (@n_curlygirl) July 23, 2024
おすすめの飲み方

ストレートでクラシカルな味を確かめる
ロックでゆっくりと変化を楽しむ大きめの氷に注いで、時間が経つにつれて味わいが変化するのを楽しむのもおすすめ。
最初は濃厚な甘さ、氷が溶けるにつれて穏やかになり、爽やかな余韻が出てきます。
水割りで食中酒に
和食や家庭料理と合わせるなら水割りが最適。
甘みがすっきりと広がり、ご飯や味噌汁など和の献立ともよく合います。
アルコール感が和らぐので、食卓で自然に飲める一本になります。
ハイボールで軽快に
ローヤルの甘みと香りを爽やかに楽しむならハイボールが向いています。
炭酸で広がる香りは軽やかで、揚げ物や塩気のあるおつまみとも好相性。
現代的な飲み方として人気です。
まとめ
サントリーローヤルは
・甘すぎる
・パンチがない
といった理由から“まずい”と感じる人もいますが、それは嗜好や期待値とのズレによる部分が大きいです。
一方で、
・蜂蜜のような甘さ
・和食との相性
・日本のウイスキー史を感じられるストーリー性
など、多くの魅力も兼ね備えています。
飲む人やシーンによって印象が変わるクラシカルな一本。
最初はストレートで味を確かめ、次に水割りやハイボールでアレンジすると、その奥深さをより楽しめるでしょう。