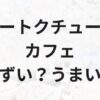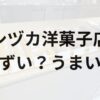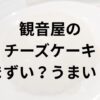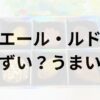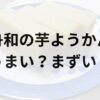金沢高木屋の紙ふうせんはまずい?まずい理由6選まとめと口コミも
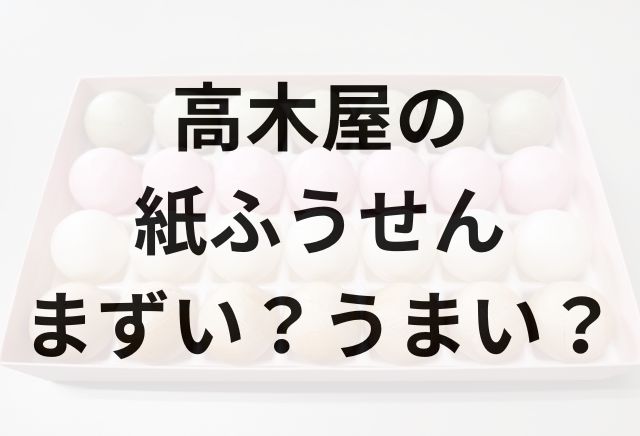
金沢の銘菓として知られる「紙ふうせん」は、見た目の美しさと繊細な味わいで観光客やお土産として人気を集めています。
しかし、一方で
・期待して食べたら拍子抜けした
など、否定的な声も少なくありません。
菓子の評価は人それぞれの嗜好に大きく左右されるものですが、なぜ紙ふうせんは賛否が分かれるのでしょうか。
本記事では「まずい」と感じられる理由と「うまい」と高評価される理由を両方整理し、さらに楽しみ方やアレンジまで含めて多角的に紹介します。
金沢高木屋とは

出典:https://takagiya.base.ec/
金沢高木屋は、明治44年(1911年)に創業した老舗和菓子店です。
加賀百万石の伝統文化が息づく金沢において、茶の湯菓子や四季折々の上生菓子などを提供し、地域の人々や観光客に愛されてきました。
その中でも特に有名なのが「紙ふうせん」という銘菓です。
カラフルな最中皮の中に小さな錦玉(寒天で作られた琥珀糖のような菓子)が入っており、見た目はまるで小さな紙風船のようなかわいらしさがあります。
パステルカラーの最中皮と中の透明感ある錦玉のコントラストは、SNS映えすることもあり注目を集めています。
金沢の和菓子文化を象徴する存在である一方、その独特の味や食感が好みに合わない人もいるため、評価は真っ二つに分かれるのです。
まずい理由

見た目と味のギャップ
「紙ふうせん」は色鮮やかで華やかな見た目から「きっと味も濃厚で美味しいに違いない」と期待されがちです。
しかし実際には、最中皮は軽く、中に入っている錦玉も非常に上品な甘さであるため、
・見た目の派手さに比べて淡泊すぎる
と感じる人が多いのです。
期待値が高い分、その落差が「まずい」と捉えられてしまう要因になっています。
食感の物足りなさ
最中皮はサクサク感というより、薄くて軽い食感に仕上げられています。
そのため「パリッとした歯応えを期待したのに、すぐにふやけてしまった」との声もあります。
さらに、中の錦玉も柔らかすぎたり、逆に固めに感じることもあり、食感全体のバランスが好みに合わない人にとっては物足りなく感じられます。
甘みが控えめすぎる
和菓子に強い甘さを期待する人からすると、紙ふうせんは非常に淡泊です。
「せっかくお菓子を食べるのだから甘さを堪能したい」という人にとっては、甘さ控えめな錦玉は物足りず、
・味気ない
と評価されることがあります。
ボリューム不足
紙ふうせんは見た目のサイズはやや大きいのですが、最中皮が軽いため、食べてみると意外と中身が少なく感じます。
結果として
・あっという間になくなってしまった
といった印象を持たれ、「まずい=期待外れ」という評価につながるのです。
日持ちや保存性による味の変化
紙ふうせんは乾燥や湿気に弱く、保存状態によっては皮がしんなりしてしまったり、逆に固くなってしまうことがあります。
購入時は見た目が美しくても、実際に食べる時点では食感が落ちてしまい、「まずい」と感じられることも少なくありません。
観光土産として長時間持ち歩かれるケースも多いため、保存環境の違いが食味の低下につながりやすいのです。
値段に見合わないと感じる人も
紙ふうせんは老舗和菓子店の商品であり、見た目やブランド性が重視されているため、価格はやや高めです。
しかし実際に食べると「味は普通なのに値段だけ高い」と感じる人がいます。
特に量や食べ応えを重視する層にとっては、コストパフォーマンスの面で不満が残りやすいのです。
うまい理由

見た目の華やかさ
紙ふうせんは、まず一目見た瞬間に心を惹かれる美しさがあります。
白やピンク、黄緑、淡い水色などの最中皮は、まるで春の花びらのように柔らかい色合いを持ち、食べる前から気分を華やかにしてくれます。
中から顔をのぞかせる小さな錦玉は、透き通るガラス細工のようで、光に当てるとキラキラ輝きます。
多くは「食べる前に写真を撮りたくなる」と口を揃えます。
味覚に入る前の視覚的満足感が強いため、それだけで「美味しい」という印象を先行して与えてくれるのです。
上品で繊細な甘さ
和菓子文化の本質は「甘さ控えめ」にあります。
紙ふうせんの錦玉は砂糖を多く使いながらも、寒天の清涼感によって後味がすっきりしているのが特徴です。
食べた瞬間はほんのりとした甘みが広がり、その後に余韻がさっと消えるため、くどさがありません。
・甘いものが苦手な自分でも楽しめた
という声も多く、繊細な甘さが人を選ばない魅力を生み出しています。
特に抹茶や濃い煎茶と合わせると、渋みと甘みのコントラストが絶妙に調和し、日本茶文化と一体となった美味しさを感じられます。
軽やかな食感
最中皮の薄さは「物足りない」とも言われますが、裏を返せば「口に残らない上品さ」として評価されます。
噛んだ瞬間にふわっと崩れ、中の錦玉と一体化して舌の上でとろけていく感覚は独特です。
特に年配の方や子どもにとっては、この軽やかさが
・口どけが優しい
と好印象につながります。
チョコレートや洋菓子のような重厚感とは違い、あっさりとした食感が「また食べたい」と思わせる要素になるのです。
季節感を感じられる
日本の和菓子は四季を映し出すものが多く、紙ふうせんもその一つです。
錦玉の透明感や涼やかな輝きは夏の清涼感を演出し、カラフルな最中皮は春の花や秋の紅葉を思わせます。
そのため「どの季節に食べても情緒を感じられる」と評価されます。
また、海外の人にとってもこの色彩感覚は新鮮で、「日本的な四季の美を味わえる菓子」として高く評価されることがあります。
単なるお菓子を超えて文化体験として味わえる点が「美味しい」という印象を強めるのです。
SNS映え・話題性
現代の消費において「美味しい=体験の総合評価」であり、その中には見た目や話題性も含まれます。
紙ふうせんはその華やかな外観から、SNSなどでしばしば話題になります。
特に若い世代は「味は淡泊でも、見た目のかわいさと特別感があるから好き」と評価します。
旅行先で買った紙ふうせんを写真に収め、「金沢らしいお土産」として共有することで、食べる以上の体験価値を得られるのです。
このように「SNS映えする美味しさ」が紙ふうせんの大きな魅力となっています。
贈答用に最適
紙ふうせんは自分用のおやつというよりも、贈答用としてその真価を発揮します。
老舗・高木屋のブランド力は信頼の証であり、箱を開けた瞬間の華やかさは「特別なおもてなし」にぴったりです。
実際に
・親戚への手土産にしたら子どもが大喜びだった
といった体験談も多くあります。
味はもちろん「贈り物としての気遣いが伝わる」点が、美味しさ以上の評価を後押ししています。
口コミ

(✪ω✪)
金沢は高木屋さんの「紙ふうせん」ってお菓子、可愛すぎません??
丸いモナカ生地の中にジャリジャリのゼリーが入ってるの!!
そして値段のキュートさよ♡
お土産に超オススメ♡ pic.twitter.com/7RaUvBDwE5— チハルこぱんだ (@chiharu_kpnd) March 9, 2025
高木屋 紙ふうせん
中身知らんで食べたらびっくりした
こういうの良いね pic.twitter.com/B1Eb2BRMcu— いわつき (@ke_ni_wa) July 27, 2025
高木屋さんの紙ふうせんスイカ届いた!
スイカ味のザクザクしたゼリーと種のチョコが美味しい😋
見た目もめっちゃかわいい🍉 pic.twitter.com/uLFJdRE8N7— リンリン (@samon_Link) August 31, 2024
この間菓匠 高木屋さんに行って買ってきた紙ふうせん、これ美味しいですね。食べる前に説明を見てイメージしてたけど、なるほど、こういう感じなのか。 pic.twitter.com/7j5FM7XwBP
— CROSS (@CROSS__KK) June 8, 2025
高木屋の紙ふうせん。
秋冬限定のいちご味とみかん味。甘くて可愛くて美味しい!
折紙が入ってて
紙ふうせんの折り方も書いてあります。 pic.twitter.com/YWgjjZUz94— りんりん (@rinrin714rinrin) March 4, 2024
おすすめの食べ方やアレンジなど

お茶と合わせて
もっともスタンダードな楽しみ方は、日本茶や抹茶と一緒にいただくことです。
渋みのあるお茶と紙ふうせんの優しい甘みが合わさることで、全体のバランスが整い、より美味しく感じられます。
冷やして食べる
紙ふうせんは冷蔵庫で軽く冷やすと、錦玉の食感が引き締まり、爽やかな口当たりになります。
夏場など暑い時期には特におすすめの食べ方です。
アイスやヨーグルトと一緒に
紙ふうせんを砕いてアイスやヨーグルトにトッピングすると、見た目も華やかで新しい食感を楽しめます。
和洋折衷のアレンジとして人気があり、子どもにも好まれる食べ方です。
炭酸飲料やカクテルと合わせて
錦玉の爽やかさは炭酸飲料やカクテルとの相性も良いです。
お菓子でありながらデザート感覚で楽しめるため、ホームパーティーなどでも映える一品になります。
手土産・贈答に活用
自分で食べるだけでなく、贈り物として渡すことで
・珍しい
と話題になり、喜ばれることが多いです。
アレンジというより活用法としておすすめです。
まとめ
金沢高木屋の紙ふうせんは、その可愛らしい見た目と上品な味わいから人気のある銘菓ですが、同時に「まずい」と評価されることも少なくありません。
・甘さ控えめな点
・食感の独特さ
などがマイナスに感じられる要因です。
しかし、逆にそれらは
・お茶に合う
・贈答に最適
と高く評価されるポイントにもなります。
つまり、紙ふうせんは食べる人の嗜好によって大きく印象が変わるお菓子なのです。
工夫次第で美味しく楽しめる余地も多く、贈り物やアレンジによって新しい魅力を発見できるでしょう。